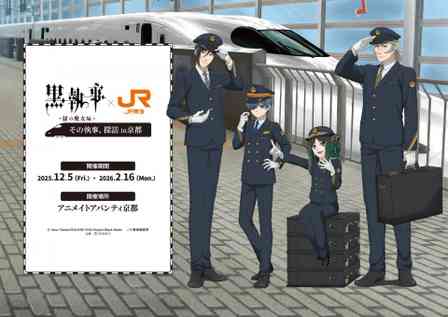一度「ゼロ」になった街は、支え合いのなか甦る 冬の南相馬・小高で感じた熱いくらいの「温かさ」
旅の終着点にも移住者の姿

双葉屋旅館の小林さん、小高工房の廣畑さん、故郷喫茶カミツレの吉田さん、Horse Valueの神さん。小高で挑戦する人たちはみんな情熱的で、まっすぐに前を向いていた。
そして初対面である筆者を、まるで小高の住民のように自然と受け入れて、話をしてくれる。
それはまるで、田舎に住む親戚と会って、再会を喜ぶような心地よさ。
小高の人々にすっかり温められた筆者は、ホカホカの気持ちで自宅に帰ることにした。小高駅に向かい、電車が来るのをホームで待つ――のだが、さすがに福島の冬は冷える。どこか寒さをしのげる場所がないかと思っていると、駅員室に普通に一般人が入っていくのが見えた。
入ってもいいのか、と後に続いた筆者の目の前に現れたのは、駅員室を改装したフリースペース。そして、そこにいたのはJRの職員ではなく、「駅もり」という聞きなれない役職の人だった。

無人駅である小高駅に駐在する「駅もり」は地域住民や駅を利用する学生たちを見守りながら、イベントを企画するなど、地域の内と外を繋ぐ役割を担っているという。
21年、この「駅もり」に就任したのが、菅野真人(かんの・まさと)さん。話してみると、彼もまた移住者だ。移住してきてまだ1年ほどしか経過していないが、しっかりと「小高の良さ」を感じている。
「小高の人たちは移住者慣れしていて、僕みたいな人にやさしいんです。引っ越してきてから、1人暮らしの僕に食べ物の差し入れをしてくれる人もいて、すごく助かりました。
それに移住してから地域の人と交流する機会が増えたように思います。コンビニも数が少ないので同じところに行っていれば、必然的に店員さんとも知り合いになりますし、メインストリートも駅前の道1本しかないので、すれ違う人も決まってきます。料理教室に行けば何かとおすそ分けをもらえますね」
菅野さんはすっかり「駅もり」として地元住民や通学で訪れる学生たちと馴染み、人がいない時間に子供を連れて駅に遊びに来てくれる人もいるそうだ。
小高に帰ってきた人、新しく小高にやってきた人。それぞれが挑戦をしながら、小高という街を再び形作っていく。それを可能にするのは、お互いを見守り、支え合う眼差しなのだろう。
なにかチャレンジを始めるなら、こんな場所でやってみたい――そう思わせる熱いくらいの温かさが、小高にはあった。
<企画編集・Jタウンネット>