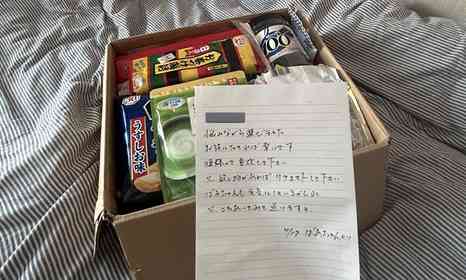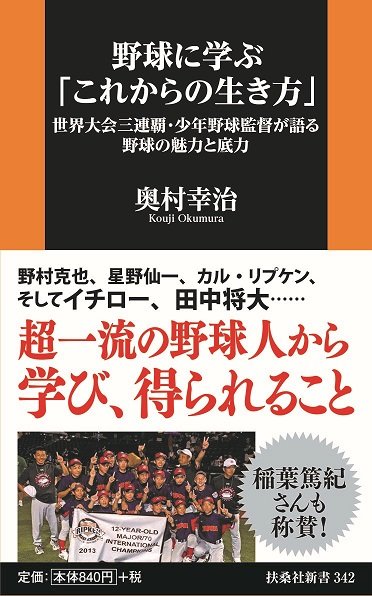まずは「この私」にエールを! ~Withコロナ、Afterコロナの「道しるべ」(第2回)~
PR
東京・信濃町にある真生会館の理事長を務める森一弘さんは、カトリック司祭(神父)の立場から、キリスト教について学びたい人や宗教に関わらず、人生そのものや生きるということについて考えたいと思う人たちのために、さまざまな講座・講演会を主宰すると同時に、50年以上もの間、相談に訪れる多くの悩める人や苦しむ人に向き合い、その声に耳を傾け続けてきました。
11月28日に新発売された『「今を生きる」そのために』(扶桑社)では、そうした森さんの長年の体験から、誰しもに覚えのある「苦しみ」や「不安」「心の傷」怖れ」「無関心」などについて、それらをどのようにとらえ、そこからどのようにしたら抜け出せるかを、具体例を交えながら、わかりやすく紹介しています。明日を拓いていくためのきっかけを見いだしていけるように、7つの章から成る本書に因み、7回にわたって、本書の内容を紹介していきます。