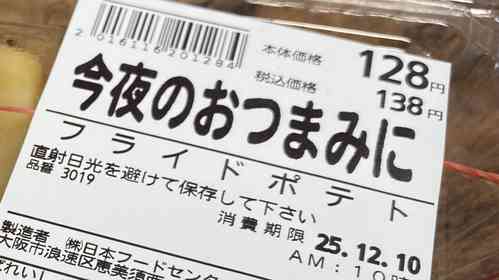83歳筆者の〈極私的鑑賞ノート〉(1)...戦中・敗戦直後の思い出の映画たち

1933年(昭和8年)生まれのぶらいおんさんは、このほど83歳を迎えた。戦中から戦後、そして現代にいたる時代を生きてきた中で、どんな映画や演劇などをその目で観てきたのだろうか。
今回から、通常の連載の合間に、不定期にぶらいおんさんの「極私的鑑賞ノート」を掲載していく。初回は、戦時中から敗戦直後までの、思い出に残る映画を中心に語ってもらう。
最も古い記憶は、夏の夜の野外上映会
映画や演劇は好きなジャンルである。
だが、自身の人格形成に影響を与えたのは(といえば、有名人の生い立ちでもあるまいに、些か大袈裟に聞こえるが)、映画、演劇には留まらない。そこで、これらを中心に置くが、それに留まること無く、広くアート全般に思いを巡らせながら、極私的に鑑賞者の立場で、余り系統的ではないけれど、なるべく時代の流れに沿って鑑賞し、体験したアートが、80年余(すなわち、昭和の殆どおよび引き続く平成の30年近くにわたり)生きて来た一人の市井の徒に、どのように影響を及ぼしたか?について述べてみよう。そして、述べるに当たり、そのベースは、主として(これまでの人生の三分の二を過ごした)東京に置くことにした。
書いてみたいことは、アトランダムに頭の中に浮かんで来るが、成るべく羅針盤の針が、あちこち飛び回らないように、小さな目標を取りながら、船を進めるように努めて行こう。
先ず、幼い頃、映画について、最も古い記憶として残っているのは、確か小学生の極低学年の或る夏のことで、場所はその頃生活していた東京では無く、紀南の小さな村、そこには父の生家があり、その本家には、父の長兄の家族たちが住んでいた。だが、その時、当主たるべき、その長兄は既に此の世に無く、残された家族のみの世帯であった。つまり、筆者から言えば、父方、伯父の家族たち、すなわち、その当時は健在の、残された伯母、従兄姉たち、それと祖母(父の生母)というメンバーであった。
従兄姉たちは全員筆者より年上ではあったが、末っ子の従兄は2歳だけ筆者より上であった。本家がこんな状態で女子供だけの所帯だったため、旧家であったこともあり、後見人の役割を果たす者が求められる状況で、結局その役目を負ったのが、この家から出た三男(次男は中学生時代に夭逝)である筆者の父であった。父は当時、東京の歯科医学専門学校の教授を務めていたので、夏休みなどが普通のサラリーマンより長かったりして、ちょくちょく里帰りするには都合がよかった。そして私の父は、よく自分の子どもたちを外に連れ出した。特に、長男であった筆者は可成り幼い頃から父のお供をする機会が多かった。
筆者の記憶では、戦争が激しくなる前は、小学生の極低学年の時から毎夏休みは殆ど、この紀南半農半漁の小村に所在する、専ら林業を生業とする本家で、従兄弟達家族と過ごしていた。しかも、大体は私を連れて来た父は途中で一旦帰京し、夏休みの終わり頃に再び筆者を迎えに来るという状況であったから、その間2ヶ月くらいの期間は伯母の家族たちだけと一緒に暮らすことになった。
毎日、大広間で机を並べて宿題を早々に片付け、後は専ら海へ出掛けて泳ぐか、魚釣りをして過ごした。そんな或る日のこと、従姉たちに、今夜小学校の広場で映画上映会があるから、観に行こうと誘われ、晩ご飯を早々に済ませて、半里(2 km)ほど離れた小学校の校庭まで涼しくなった夜道を歩きながら、その夜、上映される映画について予め教えられた、というより「とても怖い映画で、夜寝られなくなっちゃうよ」と散々脅されたが、その映画の題名は「四谷怪談」で、お岩さんと言う怖いお化けが出るという。そんなものに興味は無かったが、涼み方々珍しい上映会場に出掛けることには興味があった。実を言うと、この映画についての記憶は全く無い。製作会社が何処で、どんな俳優が出ていたのか?そしてその内容に、本当に怖い、と感じたのかどうかすら、思い出すことが出来ず、ただ話の巧みな従姉たちが「本当に怖い映画なんだよ」と繰り返していたことだけ記憶している。
これが、物心ついてから観た最初の映画だったかも知れない。だが、それより、この上映会場となった、夜の小学校の校庭に大きな白い幕を張って上映するスタイルは、小学生の頃筆者が居住していた池袋駅から徒歩で15分乃至20分位入った住宅街の中にあり、筆者も通っていた小学校でも行われることがあった。上映されたのは、当時主流であった戦争物であった、と記憶する。つまり、田舎だけでは無く、映画館のある東京でも時には、こんなスタイルで夏の夜などに映画が上映されていたのである。
戦時中、映画館で観たもので、記憶に残っているのは戦争物の「ハワイ・マレー沖海戦」とか「加藤隼戦闘隊」で、後者のテーマソングは大いにヒットし、ラジオなどでもよく放送されていたので、今でも出だしの「エンジンの音 ごうごうと...」の歌詞もメロディもよく覚えている。もし、カラオケで唱えば、歌いきる自信はある(閑話休題)、それより前で記憶に残るのは柔道映画の「姿三四郎」で、藤田進の扮する姿三四郎が師(嘉納治五郎をモデルとする?)に叱責されて蓮池に飛び込み、夜が白々と明けるまで水中で反省する、というシーンが今でも目に焼き付いている。映像シーンとして特に印象に残っているのは、夜明け頃になると蓮池からもうもうと水蒸気が立ち上っていたことだ。今、考えると明け方には気温が低下して、水温の方が高くなり、その結果、水蒸気が立ち上っても不思議では無いわけだが、当時は賢しげに大人の小細工を見通した気分で、『所詮、映画は作り物で、湯気は俳優を冷やさないために撮影では温度の高い湯を利用しているからだろう』などと分かったような気分で悦に入っていた。
もう一つ印象的だったのは、当時映画館では必ず、ニュース映画が併せて上映され、赫々たる戦果を上げた戦地の状況などによって戦意高揚が図られていた。テレビもインターネットも無い時代だったから、新聞、ラジオの報道を除けば、映像イメージというのは、今でもそうだが、特に当時の人々には視覚的、体感的に強烈なインパクトを与えていた、と思われる。時の権力にとって、プロパガンダの目的で世論を一定の方向に誘導するための有力なツールであったことは間違い無い。
さて、映画や演劇の鑑賞に際して、特に筆者が視覚的な印象以外に強く影響を受けたのは、いわゆるバックグラウンド・ミュージックやテーマ曲と称される聴覚的イメージである。具体的にそれらがどんなものであったか?はこれから徐々に述べることになる。
人によって感覚の違いがあるかも知れぬが、筆者に関しては、音楽の影響は非常に大きい。視覚的作品に併用された聴覚的、特に音楽の効果、影響は場合によると、その映画や演劇作品そのものの出来映えや筆者の評価に、それこそ決定的な影響を与える場合すらある。
また、映画や演劇に使われていた音楽を聴いて、その作曲家やその人の作品を気に入り、そこからレコードや音楽会の鑑賞にまで至ったケースも少なく無い。
それらの音楽には、クラシック音楽もあり、映画のテーマ曲、いわゆる映画音楽と呼ばれるイージーリスニングなど多岐に亘る。
時代を絞って行くと、筆者が中学校に入学した頃だから、敗戦直後、昭和20年代の初め頃、ようやく戦時体制から脱し、その結果我が国が当時置かれていた状況からして、専ら圧倒的に米国の影響が他と比較にならぬほど強烈だったわけで、その所為ばかりでは無いだろうが、筆者が鑑賞するのは自身の好みもあって、映画は矢張り邦画では無く、洋画が圧倒的に多かった。
輸入され、上映される映画の数から言えば、米国映画が圧倒的に優勢であった。だから、絶対数で言えば、筆者の観た外国映画の数では米国が1位となるだろうが、好みから言えば、フランス映画に軍配が上がり、その次は一時期流行ったイタリア映画、その他ギリシャ、トルコ等数少ないながら輸入された問題作などもあった。
それでも、邦画では後に評判となった「安城家の舞踏会」というモノクロ映画を観た記憶はある。ただ、70年も前の話となると、そのあらすじすら覚えが無く、また映画の内容も当時余り理解出来なかった、と思う。ただ、連れて行ってくれたのは、その頃には紀南の小村から、子どもたちの教育のため、一家揃って東京へ移住し、我が家から20分位の所に居を構えた本家の伯母と従姉たちだったことだけはよく覚えている。
映画について、当時強烈な印象を受けたのは、それまでは映画といえばモノクロ、つまり白黒映画というのが常識であったが、全編に亘り天然色に彩色された、いわゆるカラー映画が、初めて日本国内に、時期的に多少前後はあったかも知れぬが、ソ連(当時)と米国から入って来た。それらはソ連の総天然色映画「石の花」と米国のテクニカラーと呼ばれたカラー映画「ステート・フェア」であり、筆者はその両者を観た。
「ステート・フェア」*は米国の或る農業州の華やかな祭りを紹介するのがメインで、若い男女のラブストリーなどもあったかも知れない。昔の記憶だから曖昧であるのは仕方ないが、如何にもアメリカらしい色鮮やかなカラー映画であった印象が強かっただけで、他のことで覚えているのは、この映画には字幕スーパーが付されていなかったこと、かと言って「吹き替え」でも無かった、と記憶する。(もしかすると、簡単な日本語のナレーション位はあったかも知れない。)
映画は、当時の日本から観れば、リッチなシーンが次々と鮮やかな(些か派手すぎる)色彩で表現されて居て、専ら英語のみで進行したから、話の筋など問題外で、只ただその物質的豊かさに圧倒されるのみであった。
*(注)インターネット検索では、テクニカラー色彩の1945年作品で、あらすじは「アメリカ中西部のある田舎でのこと。フレイク夫妻は息子も娘も大きくなったし、主人のエイベルは年一回の州主催の共進会で養豚の一等賞を、妻のメリッサは漬け物で一等を取るのが望みである」とある。
その時代は、我々中学校にも制服はあったものの、生地が不足して(というより全く入手不可能で)、まともな制服を着ている生徒など一人も居なかった。みんな闇市あたりから流れてくる陸海軍の中古軍服を、母や祖母たちに縮めて、縫い直して貰ったものを着用するような時代であったことを想像して頂く必要がある。
一方、「石の花」*は確かロシアの古い民話か伝説を映画化したもので、当時の中学低学年の男の子の興味を引くような話では無かったように記憶する。ただ割合落ち着いた色調で映像としての印象は悪くなかったが、率直に言って、当時「へぇ!ソ連のように野蛮な国でもこんな映画が作れるのだ」と思ったことを正直に述べて置こう。
それは世の中が落ち着き始めて居たとは言え、当時未だに、戦争の悪夢、戦争の被害、悲劇に纏わる話題にも事欠かない状況であったことに思いを巡らさねばならない。
*(注)インターネット検索では、原作はソ連の民話作家 P.バジョーフがウラル地方の民話を採集して発表した『くじゃく石の小箱』 Malakhitovaya shkatulka (1939) 中の一編とある。
その後の米ソ冷戦の激化でも想像出来るように、米国の占領下にあった日本では、ソ連による赤化が極端に増幅されて警戒された背景がある上に、昔の満州からの引き揚げ者が、筆者の身の回りにも少なく無かった。実際、筆者の家にも歯科医専時代の父の後輩に当たる歯科医の未亡人と二人の幼子が満州から命からがら引き上げて来られて、一時、我が家の一室に滞在されたこともある。そうした方々から聞いた実話やマスコミの報道でも、ポツダム宣言受諾後に日ソ不可侵条約を一方的に破って満州国や、いわゆる北方領土にも攻め込んできた上、略奪や暴虐の限りを尽くしたソ連軍やソ連兵に対する印象は最悪であったのは当然で、しかも武装解除した日本軍兵士を労働力として強制的にシベリア地方に長期間抑留し、使役した状態が、その当時も依然として継続状態にあったことが更に印象を悪化させていた。
個人的にはロシア音楽やバレー、ロシア文学には、いわゆるヨーロッパのそれらとは何処か異なるオリエンタルな親近感を感じては居たのだが、これらの歴史的事実を忘れ去ることはなかなか困難な状況にあった。
勢い世の中の風潮も、あらゆることが米国を向き、米国を目指すのが普通であった。
話は変わり、今の中学生はどうか知らぬが、当時中学生だった筆者の時代は、中学生が友人同士でも、保護者の同伴無しで映画館に入場することなど通常はあり得なかった。そんな訳で米国の総天然色映画「ステート・フェア」を観に連れて行ってくれたのは、三年ほど前に99歳の天寿を全うした母の妹で、女医をしていた叔母であった。
日本で初の、いわゆる総天然色(カラー)映画は、筆者が確か高校生頃観た「カルメン故郷に帰る」であるが、今回、本コラムで取り上げている時代よりもっと後なので、その辺りはまた、続編中で触れてみたい。また、イーストマン・コダック社(現、コダック社)によるイーストマンカラーと称されたカラーの国産映画「地獄門」はそれより後であった筈だが、当時その色彩などが、ちょっとした話題となった。実は、この映画を筆者は、当時五反田にあった(株)東洋現像所(現(株)イマジカ)の試写室で観ている。今はもう此の世に無いが、当時この会社の専務を務めていたのは、筆者の義理の従兄で、つまり本家の長女である従姉の連れ合いという関係があった。
この第1回目連載では、時代としては戦時中から敗戦直後に及ぶ、筆者の乏しい記憶に基づいて、専らその時代の個人的鑑賞環境を中心に述べる結果となったが、次回ではもう少し筆者自身の、作品や俳優に対する評価や感動を伝えることが出来るケースに移行して行く心算だ。(次回に続く)