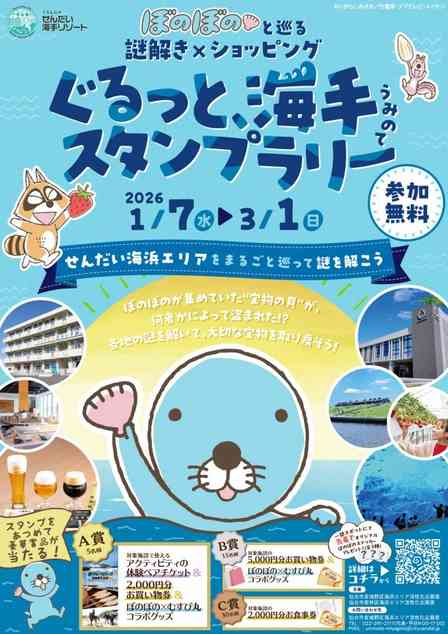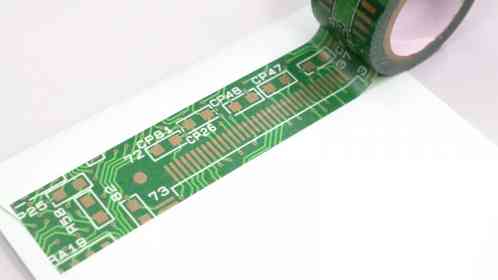受動喫煙防止条例の議論慎重に 飲食業界団体などが署名つのる
多様性・自主性を尊重したい

宇都野さんによると、組合側では、店頭に喫煙可、分煙、禁煙などを明示するという以前からの都の方針である店頭表示の徹底に長年協力してきたという。
その上で、お店によって喫煙に対するスタンスが異なることから、
「喫煙、分煙、禁煙を決めるのはあくまでオーナーの判断。そういった営業方針まで決められてしまうのは極端ではないか」
と、都が9月に公表した受動喫煙防止条例の「基本的な考え方」に対しては、それぞれのお店が抱える事情から、様々な意見が上がっていると話した。
また、宇都野さんは以前、駅から喫煙所が撤去されたことで歩きたばこやポイ捨てなどのマナー違反が増えたことを目にしたといい、
「日本の禁煙は外から始まったが、公共の場における喫煙所の整備は遅れている。その段階を飛ばし、飲食店内での規制に踏み切ると、かえって喫煙者のマナー悪化を招く恐れもある」
規制を進めることで、かえって受動喫煙を増やしてしまうことを危惧しているという。
全国生活衛生同業組合中央会、日本たばこ協会などは17年春、政府による規制強化に対して、
「たばこを吸われる方・吸われない方および各事業者の多様性・自主性が尊重され、それぞれが自由に受動喫煙防止の環境を選択できる仕組みとすること」
を目的に署名活動を行い、4月25日時点で約120万筆を集め、財務相や厚労相、官房長官らに提出した。
東京都に対して提出する今回は、街頭と並行し、10月26日から12月末までをめどとして、インターネット上などでの署名活動を行っている。小池百合子都知事は、18年2月からの都議会に条例案を出すとみられ、署名はその前に知事らに提出する予定だ。