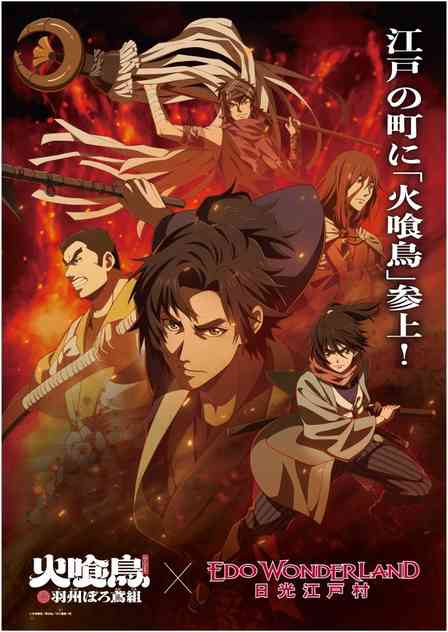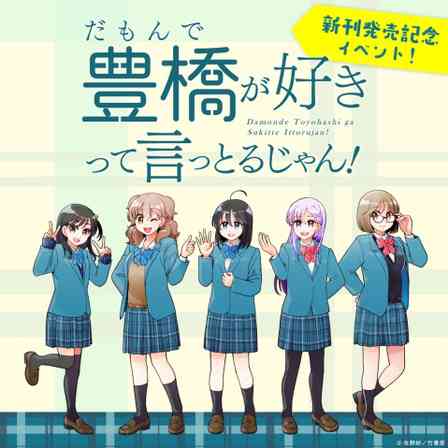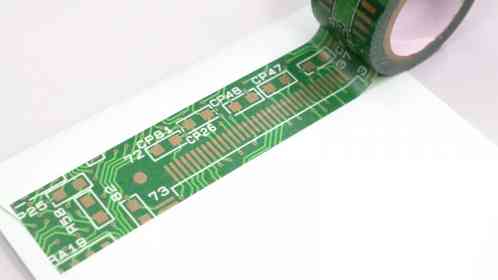花街の昔を伝える、「にし茶屋街」の風流旅
[となりのテレ金ちゃん-テレビ金沢]2015年4月20日放送の「旅のおまけマップ」のコーナーで中村神社の社殿にある能舞台について紹介していました。
石川の有名な観光地から、ちょっと寄り道したところにある隠れた観光スポットを紹介するこのコーナーで、今回は「にし茶屋街」周辺を散策しました。

金沢には「ひがし茶屋街」「主計町茶屋街」「にし茶屋街」の3つの茶屋街がありますが、にし茶屋街には一番多くの芸妓さんがおり、今でも料亭が軒を連ね、格子戸の奥から三味線や太鼓の音が聞こえてくる茶屋街です。
そんなにし茶屋街の近くにある寄り道ポイントは「中村神社」です。
いつできた神社なのかははっきりと分かっておりませんが、1685年に書かれた文書の中に「往古より中村に鎮座していたと伝えられている」と言う一文があることから、その時代には人々に親しまれていたことが分かりますね。
明治時代に消失した金沢城。なぜ能舞台だけが残ったのか?
中村神社は2004年、文化庁登録の有形文化財に指定されました。なぜかと言うと中村神社の社殿には、金沢城二の丸御殿にあった能舞台が移築されているからです。
金沢城は明治14年に起きた火災で城内の建物のほとんどを失ってしまったのですが、能舞台は、この火災の11年前に、幕末の戦乱で戦死した加賀藩士たちを祀る社殿として城下町を一望できる卯辰山に移築されていたのです。
その後30年ほど放置されていた能舞台をどこかに移したいと言う意向の中で、中村神社が社殿を改築するタイミングだったため移されたのです。
その社殿の天井には約100枚、極彩色の絵も残っているということです。当時の金沢の雅がうかがえますね。
にし茶屋街の風情を楽しんだあとは、歩いて8分ほどのところにある中村神社を訪れ、金沢城の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。(ライター:ファンキー金沢)