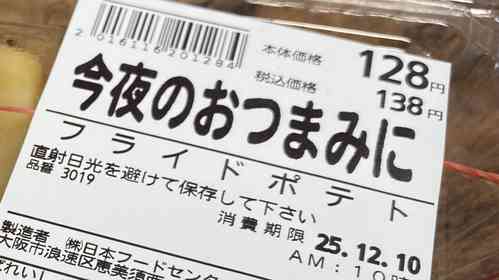「被災地を観光する」岩手県陸前高田市【後編】:造成地に未来を描く 陸前高田にかけられた橋
[文・写真 中丸謙一朗(コラムニスト)]
(前回より)中丸勝典氏は現在、陸前高田市役所の農林課に勤務している。彼は神奈川県大和市役所に籍をおくが、2011年(平成23)の東日本大震災を機に、職員の足りなくなった陸前高田市役所の「派遣部隊」として、2年以上に渡ってこの地で勤務している。わたしは震災後初めて被災地を訪れ、中丸氏の案内で陸前高田の7年後の復興の現場を歩いた。
きれいに「修復」されていく大地を眺めながら人間の底力を思い、また同時にあまり人のいない広野を見つめ、なんとも言えない空虚感を覚えた。
陸前高田はいったいどこに向かっているのか。
明るい雰囲気に満ちた「南向き」の街

立教大学観光研究所の所長である東徹(あずまとおる)教授(立教大学観光学部)は、観光の視点から被災地を見つめ支援し続ける。東教授は、東日本大震災で故郷・陸前高田に住む両親を亡くした、自らも震災被害者である。
東教授の実家は、陸前高田の大町商店街で商売をしていた。「なんとなく明るい感じのする街だった」。教授は故郷の印象をこう振り返った。
陸前高田の中心部は、南に向かって開けたU字型の湾の奥にあたる広い平地に位置していた。歴史上何度も津波に見舞われてきた地域だからなのか、市街地は平地のいちばん先、海から離れた場所に開けていた。高度経済成長時代から見れば、いまは地域の人口減少も進み、経済的活力も衰えてはきた。だが、街が「南向き」で日当たりがいいせいか、あるいは住人の人柄のせいか、街は過疎化を象徴するような暗く沈んだ感じではなく、なんとなく明るい雰囲気に包まれていたという。
震災の被害は岩手県沿岸部に広く及んでいるが、陸前高田の被害はとりわけ甚大であった。市街地は津波によって破壊しつくされた。あの日から7年もの歳月を経たいまでも、その被害の凄まじさは一目瞭然である。
人が、あるいは日本人が感じる「郷愁」のようなもの、その端緒がまるで存在しないのでしばし呆然としてしまう。そのことを伝えると、東教授はこう解説した。
「わたしたちはなぜ帰省するのか。それは親や幼なじみがいるからです。故郷の山や川とは言うけれど、実はノスタルジーの対象は人です。生まれた土地というだけでは、そこを故郷として思い続けることはできない。人のつながりが切れたら、こころが離れたらおしまいなんです。高田の人たちは故郷の土地や景色を失った。でも、人々のつながりを取り戻そうと七夕まつりを復活させた。被災地にとっての観光は、失ってしまった"地域の光"を取り戻すことなんです」

地域を支えるソフトの再生
中丸勝典さんの案内で、市内の米崎中学校の敷地内に併設されている「陸前高田グローバルキャンパス」を訪れた。これは陸前高田市の協力のもと、立教大学と岩手大学が中心となり発足した研究者、学生と地域住民たちをつなぐ「交流の場」だ。陸前高田の現状や未来を「つたえる、つなぐ、つくる」ことによって、街をソフトの部分から盛り上げていこうという試みだ。

勝典さんとキャンパス内を歩くと、ここかしこから声がかかる。勝典さんは日常の業務のほかにも、趣味やボランティア活動などを通じて、こうした地域コミュニティに時折顔を出している。彼は配属先である陸前高田市農林水産部農林課で、主に中山間地域で営農する耕作条件が厳しい農業従事者への交付金の事務を担当する。また、地域振興のための交流イベントなどにも出向き、「たかたのゆめ」(陸前高田の新ブランド米)などの地元産品の販売・宣伝にも積極的に参加している。
組織には目に見えない「ノウハウ」がある。地方行政における「住民への細やかな対応」というのもやはりひとつのノウハウなのだと思う。だが、逆を言えば、それをスムーズに生み出していけないことが組織の欠点であり、人の役に立つ知識やノウハウがきちんと蓄積されていないことが問題なのだ。
「地道なことを、その地域の人に寄り添って長い間やり続ける。それがいちばん大事なのかなと思います。いろいろな活動をするときに、公務員であることの強みもありますが、また同時に自分の任務は一時的であるという無力感も感じています」。
人が人を支えることの難しさがある。東教授は、今後の地方行政のあり方にこんなヒントを残す。
「生産年齢人口の減少で、これからの時代は、地域の人口規模・構造に見合った行政サービスが問われていくのではないでしょうか。もちろん、市町村合併も選択肢になる。そのとき、2万人規模の自治体がいいのか、10万人規模のより大きな都市の一部がいいのか、その違いをどう考えるかが問われる。また、さらに深刻化する高齢化・過疎化に対応していくには、行政だけでなく、それを補完していく地域コミュニティなどの機能を、誰がどのように担うのかということについても、考えていかなければならないと思います」。

取材を一通り終えた後、勝典さんがプライベートな時間によく訪れるという場所に連れて行ってもらった。陸前高田の北東部、平野部の脇に位置する箱根山、その中腹にある比較的新しいカフェである。表のテラス席には、東北の緑豊かな樹々に囲まれた静謐な空間が拡がる。なにもかも忘れさせてくれる、そんな時間だ。
近くにある展望台からは、湾に対峙した陸前高田の街全体が見下ろせる。恵みの海と入り組んだ陸地の輪郭線、穏やかな平野部と明るい日差しが形作った陸前高田の地。その歴史的な土地が津波よって蹂躙されるさまが脳裏に浮かび言葉を失う。いま自分が立っているここは観光地なのか。その問いは声になることもなく、ふたりは黙って街を見下ろしていた。

復興によって失うものがある
自らも被災者である東教授は、東北各地の自治体から、地域づくりについて学識経験者としての意見を求められる。岩手県内某自治体の「観光振興ビジョンづくり」もそのひとつである。
「復興によって失うものがある」と東教授は言う。
「被災地の最大の集客資源は、"被災地"であることです。観光を振興していこうとする彼らは薄々そのことがわかっている。だから被災地の匂いがなくなってしまうことを恐れてもいるのです。人々の思いとは裏腹に復興のなった新しい街は必ずしも集客力のある街になるとは限らない。人は生々しい傷跡は見たくても、治ってしまった姿など本当は興味がないのかもしれません」
復興の定義が、震災前の経済規模と同水準になることだとすれば、果たしていまの被災地はきちんとそこへの軌跡を描けているのか。また未来へと望みをつなぐ「観光行政」は果たして地域の特性を見失わずに行われているのか。取り戻す「原風景」と言っても、それはいったいいつの時代を指しているのか。本物の景色を取り戻すといっても、それはいつの誰にとっての本物なのか。
「復興とは人々の生活の場を再生していくこと。そこで暮らす人と人とのつながりを生み出し、傷ついたこころを取り戻していくこと」。東教授はこう強調した。
ノスタルジーが復興の力強いモチベーションになり、また同時に適切な復興を阻む足かせにもなる。その土地やその土地への思いが永遠に続いていく。そのことを追い求め、また追い続けることが、もしかすると「予想される」結論なのかもしれない。だが、実体はもっと儚い。人の思いは永遠ではなく、地縁血縁があっても簡単に途絶える。「三代続く」なんていう言葉がひとつの慣用句のように親しまれていた時代のスピードが速まり、もはや、二代に渡る思いの継承さえも難しい。これは被災地の陸前高田だけではなく、全国各地で起こっている。すっかり景色の変わってしまった関東平野の片隅の土地に建てられた父親の墓を前にして、わたし自身もふとそう思うのだ。

過程の積み重ねが大きな結果を生む
1977年、わたしの6歳年長の「兄貴分」である勝典さんが、この年に公開された戦争映画『遠すぎた橋』(監督・リチャード・アッテンボロー)を観に連れて行ってくれたことは、冒頭に記した。今回の原稿を書くにあたりひさしぶりに見直してみた。行く手を阻まれながらも「アルンヘムの最後の橋」を目指す無謀とも言える「マーケット・ガーデン作戦」は、上層部の思惑に振り回され多くの犠牲を伴いながらも遂行された。その様子は壮観であると同時に大きな無力感を生み出し、また、戦争という狂気があたりまえに存在していた時代背景に改めて注意を引く。
人は既成概念に捕らわれる。田舎の景色とはこういうもの。戦争は起きるもの。すべては既成概念であり因習だ。修正の機会を逸した因習は成長を阻害し、次なる世代が生み出す感動や郷愁の邪魔をする。任務に絶対の正解はない。だが、目的を見失わず事態を打開しようとする行動のひとつひとつが積み重なれば、それはけっして「遠すぎた橋」にはならない。
勝典さんは言う。「ボランティアはある意味自己満足の世界かもしれません。でも、そこには自己満足を超えて果たさなくてはならないものがある。たとえそれが小さな成果でも精一杯やったという思いは大事にしたい。最近の歌に、人生を紙飛行機に例えた歌(AKB48『365日の紙飛行機』)があります。わたしはなぜかそれに惹かれました。まっすぐな距離を競うより、寄り道をしながらもどう飛んだかどこを飛んだのかが大切、そんな歌詞を聞いて、ああ自分のやったことは間違っていなかったのだなと少しだけ安心しました」。中丸勝典氏は、3月いっぱいで陸前高田勤務の任を解かれ、無事定年退職となった。
陸前高田は、いまはまだ遠い復興への途上にある。だが、震災から7年という年月が経った街を、まるでラベルを貼って戸棚に放り込むかのように「被災地」と呼び続けることにも違和感がある。この7年の間、住民たちが作り上げてきた「造成地」としての新しい街を、今後いったいどのような色に染め上げていくのか。
「やはり(被災、二次災害による死亡、他府県への移住などによる)人口減少の進行が深刻です。ですから、市としての大掛かりな復興事業を考えることも大事ですが、人口規模を見据えた生活基盤の整備、それからなによりも、そこに住む人々が地元に誇りと愛着を持って暮らしていけるような地域コミュニティの再生が重要だと思います」。
人のこころが離れたらおしまい。東教授の残した言葉が耳に残る。いくら風光明媚でも、人の息吹に勝る観光資源はない。多くの尊い人命が失われたことに改めて深い悲しみを覚えた。【『地域人』(第32号、第33号)(大正大学出版会発行)より転載】