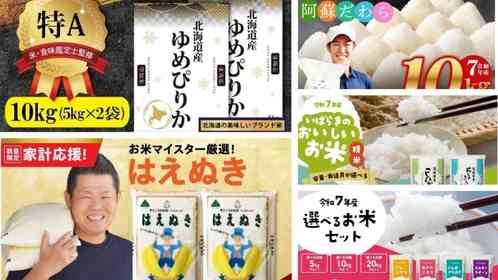冬の祭典は平昌だけじゃない! 「国際スポーツ雪かき選手権」小樽で開催
チーム力も求められるスポーツ雪かき
「スポーツ雪かき」という名前の通り、漫然とただ雪を取り除くわけではなく競技ルールがきちんと定められている。このルールによると、国際スポーツ雪かき選手権は4人チームで参加するポイント制で、3つの異なる「競技」が組み合わさっている。

まず第1競技は「ボランティア雪かき」――。選手権でいきなりボランティアとはどういうことだろうか。Jタウンネットが同選手権を主催する「日本スポーツ雪かき連盟」に取材を行ったところ、担当者は経緯を次のように話してくれた。
「もともと高齢者が多く、住民だけでは雪かきが捗らない地域で負担軽減のためにボランティア雪かきをしたいと考えていたのが選手権の発端であり、今でも主な目的のひとつでもあります。雪かきは雪国で必須の作業ですが、きつく辛いものでもあり、少しでも楽しみながらできないかと考え、競技化することを思いつきました」
そのため、選手権では必ず参加者全員がボランティア雪かきを行うことになっているのだ。その後、雪山を10メートル離れた陣地に運ぶ速さを競う第2競技「スノーショベリングアンドムーブトライアル」、既定の高さの雪だるまを製作した個数でポイントが入る第3競技「スノーマンコンテスト」を行い、総合ポイントの高かったチームが優勝となる。

ちなみに優勝チームには、大優勝旗(一年間保管、翌年返還)やトロフィー、賞状、小樽海産物詰合せ(錦屋さいとう提供)が副賞として贈られることになっており、単なるボランティアのおまけというわけではない。優勝を狙うには十分な動機が用意されている。
参加者は地元住民が多いものの、近隣の自治体や小樽市在住の外国人、さらに今年は選手権に参加するために大阪から訪れた人もおり、120人ほどの参加者がいたという。とはいえ、強豪は競技の性質上、やはりウィンタースポーツ馴れ(?)している地元チームのようだ。
「日頃の雪かき馴れが物を言うので、基本的に地元小樽市のチームが優勝していますが、過去に一度隣町の余市町チームが優勝したこともありました」
雪かきなので体力勝負なのではと思ってしまうが、担当者はいくつかのコツもあると指摘する。例えばスノーショベリングアンドムーブトライアルは制限時間が10分で、運ばなければいけない雪山は1.8×0.9×0.9メートル(フルサイズ部門の場合)となかなかの量。力押しだけではなかなかスムーズに運べないという。
「シャベルですくうのが上手い人、スノーカートで運ぶことに長けた人、4人の役割分担が非常に重要です。また、カートに雪を載せるにも馴れとコツがあり、一度に最も効率よく載せられる量を把握しておかなければ、無駄に運ぶ回数が増えてしまいます」
スノーマンコンテストでも雪だるまの形を保ちつつ、高ポイントが狙える1.5メートル以上の大きな雪だるまを積み上げるのには、「雪だるま馴れ」が求められるという。
「あまり考えずにただ雪玉を大きくしたり、積み上げているだけでは崩れてしまいポイントになりません。水を使って雪を湿らせ固めるなどの作業を随時行わなければいけません
とはいえ最終的には体力が求められるのも事実なので、女性や中学生以下のみのチーム、雪国生活5年未満のチームのために、1.8×0.9×0.45メートルと雪山のサイズを小さくしたハーフサイズ部門も用意されている。
意外に奥が深いスポーツ雪かき選手権。例年12月ごろにルール更新と大会参加受付をおこなっている。参加費は1人2000円で、参加者特典がある選手村(宿泊先、費用は自費)もある。スポーツ雪かき界のパイオニアを目指すなら、ルールブックを熟読のうえ、ぜひ第6回大会に参加したいところだ。