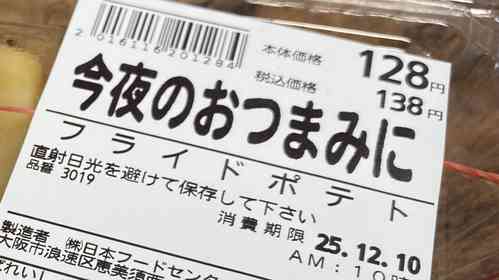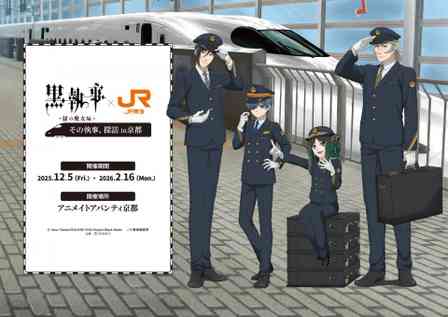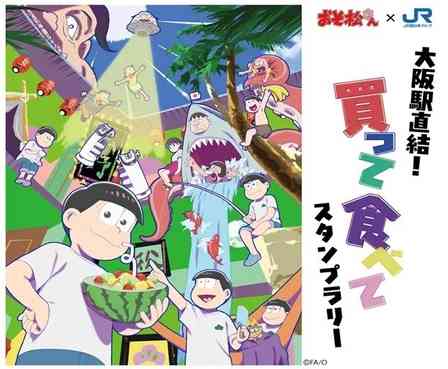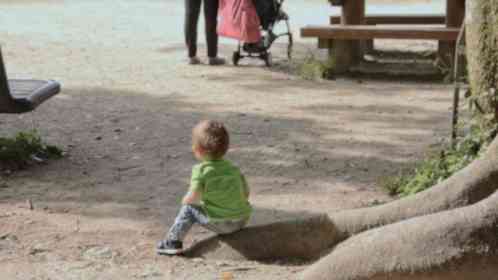江戸時代の妖怪たちが「ゆるすぎる」? 大妖怪展に登場中のかわいい幻獣たち
「ゲゲゲの鬼太郎」に始まり、「地獄先生ぬ~べ~」、「うしおととら」、「妖怪ウォッチ」と、様々な人気のコンテンツの題材となっている妖怪。そんな日本で愛され続けてきた妖怪のルーツを探る特別展「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」には、全国から集められた様々な資料が展示されている。
中でも来場者の注目を集めているのが、ゆるいタッチで数百年前に描かれた妖怪たちの姿だった。
貴重な資料多数で妖怪ファン必見
展示されている「針聞書」(はりききがき)や「姫国山海録」(きこくせんがいろく)などは、数百年前に作られたものだが、現在の漫画に通じるようなコミカルな妖怪の姿が多数収録されている。おどろおどろしいタッチで描かれている他の妖怪画とは異なった存在感を放っている。

「針聞書」に描かれているのは「腹の虫」で、当時は体調不良の原因とされていたという。「姫国山海録」には全国で見かけたといわれる珍幻獣の姿が収められている。
その「かわいすぎる」妖怪たちについて言及したツイートは700回以上リツイートされ、注目を集めた。
大妖怪展に行ってきた。250年前に描かれた下手な妖怪がかわいすぎて愛しい。 https://t.co/G6El6wEia1 pic.twitter.com/OpoTj7SJpy
— 吉永龍樹(よしながたつき) (@dfnt) 2016年7月5日
ただいまー大妖怪展面白かったよ!妖怪の絵も説明もユルいかわいいw日本人の擬人化好きは昔から変わらないねw
— おにく (@rain04equal) 2016年7月12日
地獄絵図もあるから鬼灯好きな人も楽しめると思う。
この「大妖怪展」では、日本各地の博物館だけでなく、個人が所蔵する貴重な資料も多数展示されている。巨大な人骨が印象的な、歌川国芳「相馬の古内裏」、重要文化財である京都・真珠庵蔵「百鬼夜行絵巻」を始めとする品々は、妖怪ファン必見だ。

展示会では、妖怪のルーツとして、仏教の中の地獄思想の中の生きものだけでなく、土偶という一見すると妖怪とは距離があるようなものも取り上げている。そこから中世、江戸時代と花開いていく妖怪文化を見ることが出来る。


展示物の中には期間限定のものや、日にちによっては公開されているページが異なるものもある。そのため、複数回足を運んでも新鮮に楽しめる。
更に、館内には妖怪をモチーフにした限定の飴も販売されている。同じく日本文化である精巧な飴細工とのコラボレーションも一見の価値がある。
「大妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」の開催期間は、江戸東京博物館で2016年7月5日から8月28日まで、大阪のあべのハルカス美術館で9月10日から11月6日までとなっている。