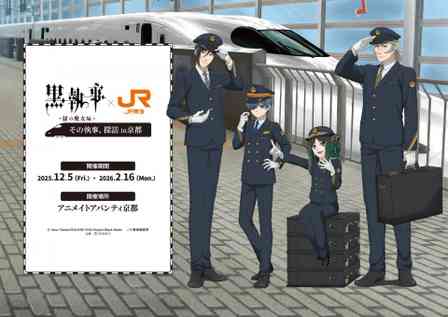各地のお月見それぞれ お団子のどろぼう歓迎の地域があった!

月は一年中見ることができますが、風習として鑑賞するのが秋のお月見です。古来よりこの時期の満月は「中秋の名月」と呼ばれており、2015年の中秋の名月は9月27日とされています。
そんな風流な秋の風物詩ですが、実際にお月見を楽しむ人はどのくらいいるのでしょうか? at home VOXでは、アンケートでその実態を確かめるとともに、地域性についても調べてみました!
「Q.十五夜にお月見をしますか?」と「Q.十五夜のお月見で団子を食べますか?」の回答結果

お月見をする人、お団子を食べる人、ともに20%以下という結果でした。意外と少ない印象ですね。なお、この回答を出身地域ごとに分析すると最も割合が多かったのは、お月見をする人36.7%、お団子を食べる人50.0%で、ともに山梨が1位を獲得しています!山梨の方はお月見はしないけどお団子は食べる、「月より団子」な人も多いんですね!
さらに、お団子といってもさまざまな種類がありますが、どんなお団子でしょうか?
Q.お月見のお団子といえば、どんな団子ですか? あてはまるものをすべて選んでください。

「プレーンのお団子」が1位! 特に東京の人は7割以上が選んでいます。シンプルな白いお団子が、ピラミッド状に積まれている、そんなイメージを抱く人が多いのでしょうね。
3位の三色団子で、回答率が最も高かったのは岡山。岡山といえばきび団子が有名ですが、お月見では三色団子なのですね。ちなみに、岡山出身者の「きび団子」回答率は13.3%。少ない数字ですがさすがは本場、こちらも全国1位でした。
お月見をする・お団子を食べる率で二冠の山梨出身者は、半数以上が「あん入り団子」と回答しているのも注目ポイントですね。次点は大阪で26.7%なので、これは非常に高い数値といえます。
お月見やお団子に関するアンケートから、地域差がうっすらと見えてきました。ですがat home VOXでは、ズバリ「Q.お住まいの地域で、十五夜の風習として行っていることはありますか?」というアンケートも実施! 寄せられた回答を見ると、お団子だけにとどまらないユニークな風習がいくつかありました。
■食べる物に関する回答
大阪「小芋を食べる」
愛知「里芋のきぬかつぎが定番です」

地方によってはお団子と同じように、里芋を供えるようです。里芋の皮をむいて塩を振ったものは「きぬかつぎ」と呼ばれています。また愛媛には野外で里芋を炊き、それを肴に宴会を開く独自の風習「いもたき」があるそうです!
沖縄「ふちゃぎをお供えする」
「ふちゃぎ」とは、餅粉で作ったお団子に小豆をまぶしたもの。豊作を祈願して神様にお供えした後に食べるそう。
■お供え物に関する回答
青森「ススキを飾り、栗や梨、リンゴ、おはぎを供える」
山梨「ススキや収穫した野菜とお団子をお供えする」
沖縄「餅を火の神様に祀る」

お団子と並ぶ、お月見の定番アイテムといえばススキですよね。アンケートを見ると、やっぱりススキを飾る地域は全国的に多かったです。加えて、野菜や果物など農作物を供える地域も多く見られました。
■催し物に関する回答
栃木「ぼうじぼを作る。米の豊作祈願の風習です」
ぼうじぼとは、栃木県各地で見られる十五夜の風習。里芋の茎と藁、縄で作った藁鉄砲で地面を叩きながら、豊作を願う行事のことです。
山梨「子どもが縁側に置いてある食べ物をもらいながら歩く」
三重「お菓子どろぼう」
地域によって呼び方は異なるようですが、「お月見どろぼう」と呼ばれる習慣が一部の地域に残っています。これは、昔は十五夜に限って畑から芋を取ってもいいとされていた風習の名残で、今では子どもたちが月見団子やお菓子をねだって回るそうです。子どもがおねだりしながら地域を回るなんて、ハロウィンとそっくりですね!
宮崎「相撲をとる」
鹿児島「相撲大会や綱引きをする」
九州南部には十五夜に綱引きをする習慣があるとか。さらに綱引きが終わったら、その綱で土俵が造られて、子どもたちの相撲大会が行われるそうです。活発なイメージのある南の地域だけあって、賑やかなお月見ですね!
お月見ひとつとっても、日本にはさまざまな風習がありますね。あなたの地域では中秋の名月の下、何をして過ごすのでしょうか?
イラスト:タテノカズヒロ
<アンケート調査概要>
対象/全国20〜59歳の男女1,410名(47都道府県各30名ずつ)
調査方法/インターネットリサーチ
調査時期/2015年8月
関連記事
芸術好きで画力にも自信あり アンケートで見えた真のアート県
アートなイメージの都道府県は? ポイントは流行、歴史、自然など
久米まりさん「人生を変えたDIY」