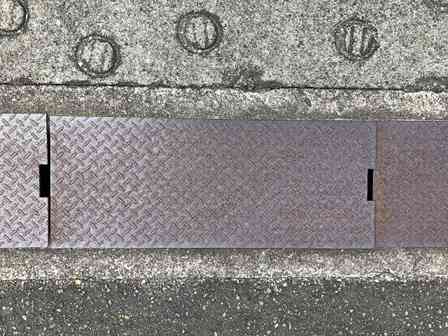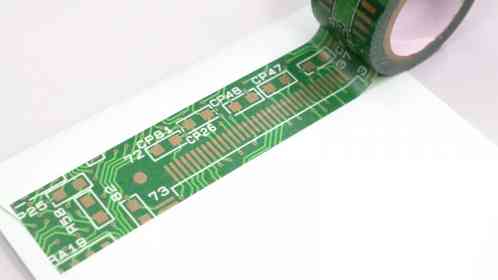本当? 日本一「暮らしやすい」街は島根県松江市だとコンピュータが判定
小中高生の子供がいるファミリーにとって「日本一」住みやすい場所はどこだろうか。東京湾岸エリアでも群を抜いて人気の高い江東区か、発展著しい武蔵小杉のある神奈川県川崎市か――。答えはいずれもノー。
日本の全1741市町村の中で最も暮らしやすいのは島根県松江市。意外な事実が経済産業省の開発したシステムによって明らかになった。

経済産業省が1741市町村を貨幣価値で評価
2015年3月30日に同省は、「地域の生活コスト『見える化』システム」を作成したと発表した。
同システムは約1万人を対象としたアンケート調査のデータがベースになっていて、コンジョイント分析と呼ばれる手法で推計された、利便性、教育・子育て、福祉・医療などの暮らしやすさに関する指標に関する貨幣価値が表示される。
全国、地域ブロック、都道府県内での上位ランキング市区町村も知ることができる。
松江市が全国1位になるのは、条件設定で「夫婦と子供(小中高生)」「40歳代」「郊外・農村志向」22種類ある「暮らしやすさ指標」を全て選んだ場合の結果だ。
トップ10のうち島根が5市、富山が3市、石川が1市、鳥取が1市となっている。島根は過疎化の進行が特に深刻だと言われているが、住み心地は一流ということか......。

郊外・農村志向ではなく「利便性志向」を選んだ場合は石川県野々市市(ののいちし)となる。
上位10市のうち福岡が4市、石川が2市、富山、福井、鳥取、山口が1市ずつランクインしている。福岡の筑豊エリアが高く評価されているのは注目に値する。

指標のチョイスは地方有利
上位に入った都市についてはあれこれ言うまい。しかし、下記の暮らしやすさ指標のうち(16)~(18)、(20)はどうみても都心部の自治体が不利。また(09)に「大学(短大除く)までの距離」が挙げられている。近ければどんな大学でもいいのだろうか――という気もしないでもない。
<生活利便性>
(01)ショッピングセンターへの距離
(02)飲食店の集積度
(03)バス停までの距離
(04)鉄道駅までの距離
<働きやすさ>
(05)通勤通学時間(※都道府県指標)
(06)地域の求人倍率 (※都道府県指標)
<教育・子育て>
(07)小中学校までの距離
(08)学校での子供に対する先生の目の届きやすさ
(09)大学(短大除く)までの距離
<医療・福祉>
(10)地域の保育所の待機児童率
(11)老人福祉施設の定員充足率(利用のしやすさ)
(12)病院又は診療所までの距離
(13)高度な救命措置が可能な救命救急センターまでの所要時間
<災害>
(14)今後30年間に、震度6以上の揺れが発生する確率
(15)津波避難対策地域(市町村単位)の該当
<自然環境>
(16)周辺での緑(農地や森林)の多さ(市町村総面積に占める、農地・森林・湖沼の面積の割合)
(17)空気のきれいさ(大気汚染物質の濃度)
(18)水のきれいさ(名水・湧水の有無)
(19)年間平均気温
<ライフスタイル>
(20)地域で採れた食材の入手のしやすさ(※都道府県指標)
(21)治安の良さ
(22)地域の活動(まちづくり、町内会、PTA活動など)に関わる人の割合(※都道府県指標)

システム開発の狙いは移住促進?
開発の目的と用途について、経産省の発表資料には次のように書かれている。
「当システムは、移住を検討する方々にお使い頂くことや、地方自治体等の移住促進を担当する方々が移住促進戦略を策定するためにお使い頂くことを想定しています」
本システムの開発には同省の「日本の『稼ぐ力』創出研究会」がかかわっている。座長はテレビ東京系の「ワールドビジネスサテライト」(WBS)のコメンテイターでおなじみ、東京大学の伊藤元重教授だ。
最後に。関東地方にエリアを限定し、単身世帯、20歳、利便性志向、暮らしやすさ指標は生活利便性の5つだけにチェックを入れて検索してみた。
1位になったのは千葉県流山市。つくばエクスプレスと東武アーバンパークラインが交差する都市である。そして東京23区は1つも入らなかった。