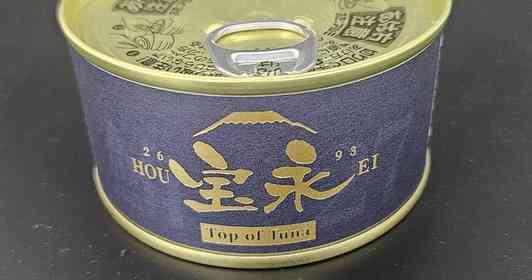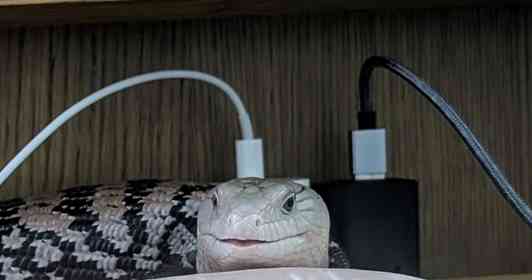意外!?「ハートマーク」は江戸時代から日本に存在した
[となりのテレ金ちゃん-テレビ金沢]2015年2月10日放送の「教えて!小倉さん」のコーナーで、ハートマークのルーツについて紹介していました。
ヨーロッパからハートの形が伝わったのは、なんと450年前
菅原道真の霊を祀る石川県加賀市にある江沼神社。その敷地の一角にある長流亭のお茶室にはハート型をした透かし彫りの欄間や庭石などがあるといいます。
さてこのハートの形はいつごろから日本にあるのでしょう?ハートマークは約450年前、ヨーロッパからトランプが伝わったときにハートやダイヤ、クラブとともに伝えられました。江戸時代初期にこれが服飾や靴、帽子の模様に取り入れられます。いわゆる『キリシタン文化』です。
近江出身の茶人で建築家の小堀遠州はこのハートマークを好んで使ったといわれます。美術関係のアドバイザー役をしていた遠州が住んでいた京都の大徳寺の茶室にはハート型をした火袋の灯篭があるそうです。
なぜ、長流亭のお茶室にハート型のらんまや庭石があるかというと、遠州は加賀藩の三代藩主・前田利常と交友関係があり、その縁で長流亭のお茶室の原型を作ったと伝わっています。
この時代にハート型を取り入れたお茶室はこれまでの伝統的なお茶室と違ってモダンなつくりだったんでしょうね。
加賀藩はキリシタン大名の高山右近が長く暮らしたことからもキリシタン文化と縁が深く、江戸時代のハートマークが伝わる長流亭は貴重な名所といえるでしょう。(ライター:ファンキー金沢)