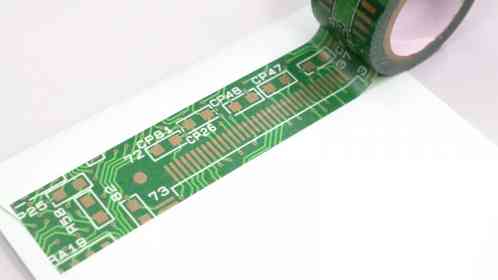広島県北部のスーパーでは「ワニ」の肉が売っている!?
熱帯に住む爬虫類の中で最も大きく、かつ独特の存在感を放つワニ。
現在の日本に野生のワニは生息していないため、動物園や映像以外で見ることは滅多にないし、毛皮や肉が販売されていることを知らない人もいるのではないか。
ワニは水場の近くにいるイメージが強いが、広島県北部で「わに」の肉が売っているという。瀬戸内海沿岸ならまだしも、中国山地近くの山奥というのは――「ホント!?」と言いたくなる。

庄原市で撮影されたスーパーの写真には......「お刺身におすすめ」として販売されている「わに(生食用)」の姿が!
といっても爬虫類のワニではない。実はこれ、「鮫(さめ)」の肉なのだ。岡山・広島・鳥取・島根の山間地では昔からサメのことを「わに(ワニ)」と呼んでおり、郷土料理が今も伝わっている。最も盛んなのは広島県三次市で、「ワニバーガー」を提供する食品店もある。
ワニ料理
http://t.co/5qlVuTHxaE
そうだ。サメのことワニって言うよね。さかなじゃなかったけどw
— さつま (@satsumabushi) 2014, 10月 13やっぱ三次はワニ料理だね
サメだけど... pic.twitter.com/DDBogEVVSB
— いまいゆう (@iimyyou) 2014, 10月 17
それにしても、なぜ山奥でサメ料理!?
通常、魚は2~3日で腐敗してしまうが、排尿器官が発達していないサメはアンモニアを貯めやすい。多くの地域ではその臭いが嫌われ、あまり食用にされないが、アンモニアの効能でサメの肉は腐りにくい。現在のように陸上輸送が発達していなかった時期でも、山奥で食べられる海産物として重宝されてきたというわけだ。

ところで、古事記に出てくる神話「因幡の白兎」(いなばのしろうさぎ)には「和邇」(わに)という言葉が出てくる。
これが何をさすかについては論争があり、中国地方の人がワニ=サメと呼ぶことから魚のサメとする説と、ワニ類だとする説がある。国学者の本居宣長や、国文学者の折口信夫はワニ類説を採っている。
サメ説が正しいとすれば、はるか古代から、この地の人々は「わに」に親しんできたようだ。