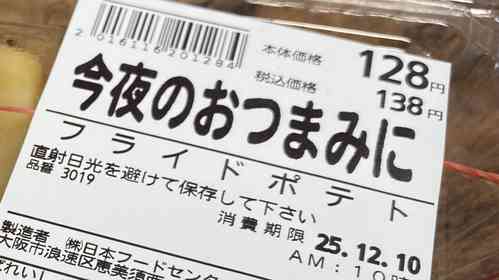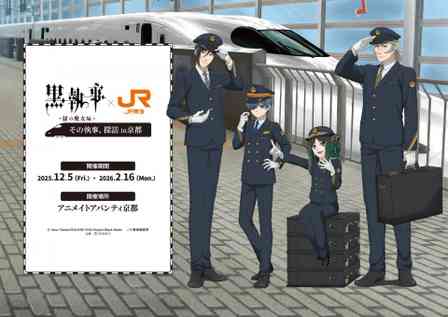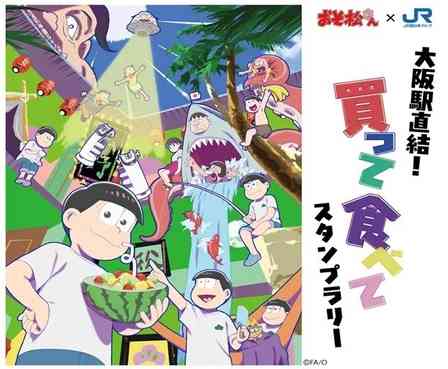神戸の歴史ある「処女塚」、一時「乙女塚」に改名? その真相に迫る
神戸市東灘区には「処女塚(おとめづか)」という交差点があり、近辺には前方後円墳が存在し、遺跡公園として整備されている。この交差点の標識に関して、『ロードス島戦記』などの作品で知られる作家・水野良さんが、次のようなツイートを発信し、注目を集めた。
自宅の近所に「処女塚(おとめづか)」という地名があり、交差点の標識にもなっていた。通過するたび鼻息を荒くしていたものだが、すこし前に「乙女塚」に改名されてしまったのだ。「ああ、教育上よろしくないので、漢字を変えたのだなぁ」と嘆息したのだが......(続く)
— 水野良 (@ryou_mizuno) 2015, 1月 10(続いた)最近になって、「乙」の字が「処」に上書きされていた。単なる誤植だったのか、あるいは誰かから抗議があって戻したのか、気になって仕方がない。事情を知っている人がいたら、ぜひ教えてほしい。
— 水野良 (@ryou_mizuno) 2015, 1月 10ちなみに、その交差点の標識の写真もツイートされていたので、ご紹介しておこう。
処女塚交差点。処の文字は上から貼られてますが、乙と間違えたのでしょうか... pic.twitter.com/S9pmTewVB0
— ざっきー地理 神戸市バス (@kobe_nonstep) 2014, 12月 25なるほど、「処」の部分が、シール貼りされていることが確認できる。
万葉の歌にも詠まれた悲恋の伝説
この処女塚という一風変わった地名は、古代から残るある悲しい伝説に由来している。
神戸市の観光コンベンション課のウェブサイトから引用しよう。
この地に美しい乙女(菟原処女(うないおとめ))が住んでおり、多くの求婚者がいましたが、特に熱心だった2人(和泉(いずみ)(大阪府南部)の"血沼壮 士(ちぬおとこ)"と地元の"菟原壮士(うないおとこ)")が武器を持っての争いとなり、乙女は立派な若者を自分のために争わせたことを嘆いて死んでしま います。
2人の若者もそれぞれ後を追って死んでしまい、それを哀れに思った人たちが、後々に語り伝えるために3人の塚を築きました。
この伝説は、万葉集の中では、高橋虫麻呂や大伴家持の歌として残されている。また平安時代の「大和物語」では、2人 の若者が水鳥を弓矢で射て乙女を争うストーリーとして紹介された。
後の時代にも、謡曲「求塚」や森鴎外の戯曲「生田川」などとして、たびたび取り上げられている。

電話で問い合わせて分かったことは?
さて伝説はともかくも、水野先生がツイッターでつぶやかれた「単なる誤植だったのか、あるいは誰かから抗議があって戻したのか、気になって仕方がない」という件に関して、編集部では神戸市役所に電話で問い合わせてみた。
神戸市役所の代表番号に電話をして、いくつかの部署にあたってもらい、建設局道路部の外郭団体である「東部建設事務所」というところにたどり着いた。ここは神戸市内の道路上の標識を設置しているとのこと。
担当者の説明によると、問題の神戸市東灘区御影塚町にある交差点には、2013年度に「乙女塚」という表示の標識が確かに設置されたという。しかし、地域の人々からの指摘と要望があり、2014年11月に旧来の「処女塚」に戻したとのこと。
なぜ「乙女塚」という表示にしたかは定かではないが、場所が交差点だけに、警察の資料をもとにしたのではないかと推測される、という話だった。
今回の件はともかくとしても、近年では市町村合併などの影響で、古くから残る地名が消えることも少なくない。いろいろの事情はあるだろうが、万葉の香りを伝える「処女塚」の名が残ったことを喜びたい。