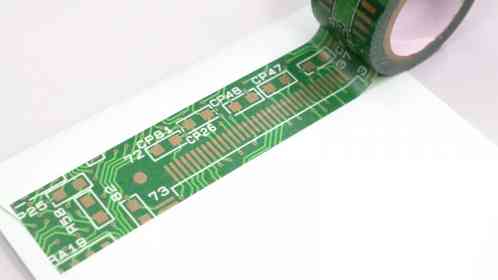面白いクイズの作り方は? 「日本クイズ協会」代表に聞いてみた

クイズ。これまでの人生で、一度もクイズに触れたことがない、という人は、まずいないはずだ。テレビにも、雑誌にも、ネットにも、そして普段の何気ない会話にも。私たちの日常には、クイズがあふれている。
一方で、実際に試合をしたり、大会に出たり、となると、意外とハードルが高い。スポーツなどのように、身近に部活やサークルがあるわけでもないし......。
こうした「クイズに興味はあるけど......」という初心者、特に若い世代にも、クイズを楽しんでもらうことなどを目指して活動しているのが、一般社団法人日本クイズ協会だ。Jタウンネットでは代表理事の齊藤喜徳さんに、その活動や、面白いクイズの作り方を聞いてみた。
クイズ番組の常連が集まって

「2016年12月から、公式サイトも立ち上げるなど、本格的に活動を開始しました」
都内の編集部を訪れた齊藤さんは、協会の立ち上げをこう説明する。
齊藤さんをはじめ、協会の中心メンバーの多くは、テレビの視聴者参加型クイズ番組の「常連」たちだ。1980年代の全盛期には、週に何本もこうした番組が放送されていたが、やがてブームは下火に。世間のクイズ熱も冷め、齊藤さんもこの世界から離れていた。
しかし最近では、テレビ番組などの場に限らず、同好の士たちが集まり、「草の根」的に大会を開くなどして、クイズ文化が盛り上がりを見せつつある。こうした熱気に触れ、齊藤さんもクイズの現場に復帰したのだという。
一方で齊藤さんは、クイズをめぐる現状に課題も感じている。
「たとえば中高生がクイズに興味を持っても、ほかの文化部のような公式の大会がなく、『オープン大会』と呼ばれる休日などに愛好者がボランティアで開催している大会しかありません。とはいえ、ハイレベルな大人が集まる大会やサークルにいきなり参加、というのはハードルが高い。良くも悪くも閉じた世界で、初心者が少しずつ入っていく、という仕組みがないんです」
小中高生向けの「体験会」を実施
そこで協会では、特に中高生など若い世代に対し、クイズの世界の門戸を開くことに取り組んでいる。
たとえば2017年8月20日には、ワークショップ「高校生以下クイズ体験会」を東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催する。小中高生を対象に、定番の「早押しクイズ」などが実際に体験できる催しだ。こうしたイベントを通じ、クイズ文化の裾野を、主に若い世代に対して広げていくことを目指しているという。8月1日からは、協会の会員募集もスタートした。
面白いクイズの作り方は?
15日からは、Jタウンネットの姉妹サービス、クイズ・診断サイト「トイダス」でクイズ投稿コンテストが開催される。日本クイズ協会は、コラボレーションの形で、出題された問題の審査なども務める。
面白いクイズを作るには、どうすればいいのだろうか。
「『問題と答えを聞いて、へぇ~となるのが面白い問題。はぁ~?となるのがつまらない問題』――ちょっとした豆知識が含まれていたり、構成や選択肢がよくできていたり。そうした部分で思わず人に出してみたくなるのが、面白い問題だと思います」
「問いかけ」というのは、日常のコミュニケーションでも、話を弾ませるための基本だ。片方が一方的に自分の知識、うんちくを自慢するばかりでは、会話は続かない。クイズも同じだ。
クイズの形式ごとにまたコツは違ってくるという。たとえば、定番「○×(マルバツ)クイズ」では、「いかに嘘のような○の問題を作るか」が難しいと語る。単にマニアックな知識を持ちだして、「○か×か」と聞くだけでは、解答者には「わざわざ出題するということは、きっと○だろう」と心理を読まれてしまうからだ。
間違っても「そっちだったか!」と思わせるような
また複数の選択肢から答えを選ばせる「択一式クイズ」なら、
「理想は、正解のほかに、こっちが正解かも?と迷うような選択肢があることですね。意地悪すぎると解答者に不満を感じさせてしまいますが、巧妙に迷わせるような選択肢だと、不正解となっても『あ~、やっぱりそっちだったか』と納得がいきます」
回答者をうまく「迷わせる」。まさに「へぇ~」となるような問題作りが、やはり重要のようだ。
「やはり最初は『答える』方が楽しいと思うんですけど、問題を『出す』側の楽しみにも気づいていただければ。協会でも普及のため、問題の作り方やイベントの開催のやり方なども、アドバイスしていきたいと考えています」
協会としては今後、クイズの社会的な認知度を高めていき、公的な大会の開催や、「段位」や「級」のような仕組みの構築も目指したいという。いつかはそうしたクイズの実績が、進学や就職の際にアピールポイントとして使えるように――齊藤さんはそう夢を語る。
「これから初心者向けの体験会などや、支部などの整備を通じて、安心してクイズを楽しんでもらえる環境を作っていきたいと思っています。どうか安心して門戸を叩いてもらえれば」