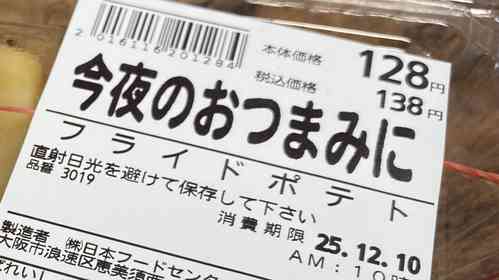消失する日本の往来――「消滅可能性都市」の現在/十津川村
第2回 消えゆく「山仕事」、消えた映画館
十津川村の面積は672.38平方キロメートル。東京23区を合わせたそれよりも広い、日本の最大の面積を持つ村である。そして、その96%を森林が占める。いくつもの山が連なり、その間を毛細血管のように無数の谷が交差する、それが十津川の地形である。村人は、奇跡的に形成されたわずか4%の平地に、家を建て、道を敷き、畑を耕し、やがて、橋を架け、祭に集い、学校を造り......そんな営みを太古の昔より続けてきた。十津川村の往来とは、そんな風景である。

中世から近代、現代へ。村の景色は都市の思惑で変わっていった
圧倒的な山と森林、と言っていいだろう。スギとヒノキが半分を占める森が、視界に入らない場所を探すことは、十津川では不可能だ。十津川の人々は、常に山と森林を視野のどこかに置きながら暮らしてきた。山とともに、山の民として。「自然との共生」などという近年のキャッチフレーズが陳腐に思えるくらいに、十津川も十津川の人々も、ごくごく当たり前に、この圧倒的な山と森の中に生きてきたのだ。こんな民話が残っている。

十津川の山並みは、人の進入を拒むかのようにどこも屹立している。
上湯川の古谷川の上流に上(かみ)という家があった。今では屋敷跡だけが残っている。
ずいぶん昔の話である。この家におさよ、という娘がいた。ある日のことである。おさよは、日が暮れても一向に帰ってこなかった。家の人は大さわぎをしてさがしたが、何の手がかりもなかった。村の人も次の日から手分けをしてさがしたが、全くどこへ行ったかわからなかった。
おさよが突然消えてからというもの、家の人は、何とか無事に生きて帰って来てほしいものだと、一心に神様や権現様にお祈りし祈とうも続けた。それでも、おさよは一向に現われなかった。
ところが、まる三年過ぎたある日、おさよがひょっこり帰ってきた。
あわれにも、おさよは見るかげもない姿であった。着物はぼろぼろになり、歯は一本もなかった。
みんながいろいろ聞きただしたところ、おさよのいうには、出谷奥の栂の木の本(もと)で天狗にかくまわれていたという。その間、天狗がひょいと出してくれるものは、石でも何でも食べられたという。そして、天狗のところでは三日しかいなかったはずだ、と話していたということである。
――『十津川郷の昔話』(十津川村教育委員会編)から「おさよ」――
浦島太郎の十津川村版とも言える話だが、浦島太郎が漁を営む民と海の関係性を示唆しているように、「おさよ」の話も、山の民と山のそれを示していて興味深い。山、谷、滝、峠。山の神、狐、オオカミ、タヌキ、河童、山女。十津川村は、険しい山々と深い森の作る時間と物語の中に存在している。
山を畏れ、山とともに生きる十津川の人々だが、意外なことに、この村において、いわゆる林業が盛んであったのは戦後の一時期だけだという。その理由は極めてシンプルで、近代になるまで、木材を運び出す道がなかったからだ。
十津川村と五条市を結ぶ縦貫道路、つまり十津川街道の拡張工事が始まったのが明治40年。そこから50年以上かかって、道はようやく村の南端まで辿り着く。それまで十津川は文字通り、陸の孤島だった。「十津川人は、ながく雲煙の中にいた」――司馬遼太郎は『街道をゆく』の中で、そう語っている。
1960年代の高度経済成長の時代、都市部の住宅需要の高まりに伴って十津川村の林業は活況を呈す。が、ガイザイがすぐにやってくる。安価な外国産の木材「外材」である。この「外材」に価格面で太刀打ちできず、林業の盛り上がりはあっという間に萎んでしまう。
一方、戦後、長きにわたって村の基幹産業となったのは、実は「土木」だった。こちらは、電力需要の高まりがその背景にある。1950年代に入り、熊野川の開発計画がされる中で、風屋、二津野の2つのダムが十津川村に建設することが決定した。風屋ダムの着工は1958年。前回登場いただいた玉置神社の弓場宮司の実家は、このダムの底に沈んだ。風屋ダムは着工から2年後に完成、すぐに発電を開始し7万5000kWの電力を関西圏に今も提供し続けている。


風屋ダムの完成によってできたダム湖。この湖畔に十津川温泉郷がある。
風屋ダムの完成後、ほとんど間を置かず二津野ダムの建設が始まる。こちらも2年後に完成、発電出力は5万8000kWと、村の年表には記されている。
ダム工事と平行して、縦貫道路の整備が急ピッチで行なわれた。建設資材を搬入するため大型トラック、大量の土砂を運び出すダンプカー、ミキサー車、重機、そして何より大勢の建設作業員を輸送するために、橋が架けられ、トンネルが造られ、道幅が拡張され、十津川街道は近代的な道路へと変貌していった。日本中が高度経済成長に湧く中、十津川村はようやく「雲煙」を振り払い、町とつながった。それは言ってみれば、都市の思惑によって、切り開かれた風景でもあった。
活気と活況、そして消えた映画館
久保隆さんは、この十津川に生まれ、十津川で育ち、76歳(インタビュー当時)になる今日まで十津川に留まり、村を見続けてきた。終戦、2つの大きなダム建設、村の発展と衰退。久保さんの目に映った十津川村の往来はどのようなものであったか、十津川温泉のバス停から山側に、急な斜面を2,30メートルほど上がったところにある久保さんの自宅でお話を伺った。

久保さん宅への道は急な階段。地元の人はスタスタと上っていく。
「このへんは戦争と言っても爆撃もなし。まあ、(戦争は)ラジオで聞くくらいのもんですわ。だから、終戦を知ったのは1日遅れの8月16日の夕刻でした。どうも、戦争が終わったらしい、と(笑)」
まさに「雲煙の中」。が、やがて村には大きな変化が訪れる。久保さんが高校2年生のとき、ダムの工事が始まったのだ。通学していた十津川高校へは自転車で20分ほどの距離だったが、ダム工事のため街道が使えなくなり、2年生と3年生のときは山を越えて徒歩で通ったという。

久保隆さん。2011年の大水害のときは、大雨でダム湖の水面がみるみる上昇していくのを自宅から眺めていたそうだ。公営の温泉に設けられた東屋の屋根がぷかぷか浮いているのを見ても、「別に不安なことはなかったねえ」と。この村の人はよほどことがない限り慌てたりしない。
久保さんは高校卒業後、奈良市内の大学に進学する。久保さんが十津川を離れたのは後にも先にもその4年間だけだ。
「バスで五條まで行って、電車に乗り継いで奈良まで行くんです。バスに乗っている時間が4時間半くらい。電車は1時間くらいですわ。で、そのバスがね、ダム工事の真っ最中だったもんですから、行きも帰りもダムの作業員でいっぱいでぎゅうぎゅう詰め。朝一番のバスに乗ろうと思ってバス停に行ったら、もういっぱい人が並んでて......」
当時の十津川村は、大勢の工事関係者や建設作業員で賑わっていたのだという。
「ちっちゃな映画館があって......あ、パチンコ屋もありましたね(笑)。飲み屋が一番多かったですが」
奈良の大学(奈良教育大学)を卒業後、久保さんはまっすぐ十津川村へ帰ることを選択する。奈良市内で「10年ほど働いて町を経験してからこちらへ帰る」ことも考えたという。が、結局、久保さんはそうせず、生まれた家に戻り、教員として十津川の中学校で働き、十津川で結婚し、十津川で3人の子供を育て、十津川で定年を迎えた。もし、奈良に残ることを選択してたらどうだったでしょうね? と問うと、
「それは私にもわかりません。でもまあ、結果的にこちらで楽に幸せに一生を送ることができたと思います」と。"幸せに一生を送る"――そんな重い言葉があっさりと笑顔の中から出てきた。
教員時代の教え子の卒業後の進路について聞いてみた。
「教師になってから最初の10年間は、中卒の子供が"金の卵"と言われた、そんな時代ですわ。奈良県下の繊維産業から、特に女生徒は引っ張りだこで、親のところはもちろん学校にも企業の人がよう来てましたね。だから、みんな村を出て行くんです。で、ほとんどは向こう(村外)で結婚して、こっちに帰ってきても仕事が少ないですから。特に女の子はほとんど仕事がそのころはなかったですわ」
男生徒は、村が林業で潤っていた時期は「山仕事」をするために十津川に残る子が多かったのだそうだ。
「植林やら伐採やら、そういう山仕事がいくらでもあったんです。高度経済成長で材木がいくらでも売れましたから」
が、先に述べた「外材の流入」によって、「木を切ってもほとんど売れなくなった」と。若い人たちは林業を諦め、仕事を求めて村の外に出て行ったという。この話をしていたときの久保さんは、少し寂しそうに見えた。
インタビューはこのあと、初めてテレビを買ったときのこと、3人のお子さんの話、伊勢湾台風の体験、そして2011年の大水害のことなど、話は尽きなかった。中でも久保さんがその日一番の笑顔で話し始めたのが、十津川郷士の話だった。「このへんはみんな武士の位だったんですよ。だから苗字を昔から持っとったんです。槍とかもありますよ」。鳥羽伏見の戦い、天誅組、久保さんの話は、日本史の世界を縦横無尽に駆け巡った。
久保さん宅でのインタビューを終え玄関を出ようとすると、久保さんが「柿でも持っていかんか」と声をかけてきた。久保邸は、村を貫く国道168号線の脇からやや急な坂を2,30メートルほど上がった途中にある。その斜面にはいくつもの柿の木があって、その日はほどよく熟した柿の実が数え切れないほどなっていた。久保さんはさくさくと柿の林に入って、ひとりでは食べきれないほどの実をとった。それをすべて土産にもたせてくれた。柿のオレンジ色が、十津川の山並みの深い緑によく映えていた。幸せに一生を送る――その言葉の重みをもう一度噛みしめた。

久保さん宅にテレビがやってきたのは1972年のことだったという。日本の平均からすると10年近く遅いのだが、「昔はテレビがあっても映らんかったから」と笑う。屹立した山々はテレビの電波をも拒んでいたのだ。今は、ケーブルテレビで鮮明な画像が映る。
帰りに、久保さんの話にあった、映画館があったであろうと思われる場所に行ってみた。ダム湖のほとりにあるその場所はカラオケ屋があるのみで、映画館を彷彿させるものは何もなかった。

かつて映画館があったと思われる場所に行ってみたが、それらしい跡は残っていなかった。今、村には映画館もパチンコ屋もないが、特に不便はないという。「隣の町まで行けばいいので」と、また笑われた。
>第3回へ続く